今回は、受験勉強の長期計画の立て方について書きたいと思います。
受験科目には「習得に時間がかかる科目」と「すぐに点数が上がる科目」があります。
私は、前者を「理解型科目」後者は「暗記型科目」と呼んでいます。
この記事を読む前に、2つの違いを理解しておく方が良いと思います

私の受験勉強計画
この計画を立てるにあたっての前提条件は次の通りです。
計画の前提条件
当時の私の状況をまとめると、次の通りになります。
- 10月から勉強開始
- 高校中退を半年で中退したため高校で学ぶ内容は無勉状態
- 4年間ほとんど勉強をしていない(大検の前を除く)
- 弁護士になるため、司法試験に強い大学に行きたい
- 志望校:東京大学文科一類、早稲田大学法学部、中央大学法学部

直前に受けたマーク模試の偏差値は次の通りです。
- 英語:35
- 国語:40
- 数Ⅰ・数Ⅱ:25
- 日本史:45
- 生物:60
ここから、3~4か月で、志望校の合格レベルに到達するのは無理なので、
1年半後の入試を目標に計画を立てました。
最初に情報収集を行う
当時の私は、大学受験に関しての知識がほとんどありませんでした。
- センター試験の仕組みや私大入試の仕組み
- 入試にどんな科目が必要なのか
- 勉強のやり方
- 他の受験生はどんな参考書を使っているのか
こういう基本的な知識が全くありませんでした。
何も知らずに計画の立てられないので、次のような本を読みました。
- 大学選びの本
- 参考書選びの本
- 勉強法の本
- 大学合格体験記
- 司法試験体験記
あなたが、何をしてよいかわからないなら、まずは情報収集です。
本屋でこれらの本を探してみたり、色んなサイトをまわって情報を集めましょう。
では、まずは基本方針を決めなけばなりません。
基本方針を決める
「暗記型科目と理解型科目の違いを知っておく」という記事で書きましたが、
受験科目には、時間がかかるものとそうでないものがあります。
- 時間がかかる科目:理解型の科目の英語や国語、数学等
- 時間がかからない科目:暗記型の科目の日本史、生物、地学等
このため、「1年間で受験勉強に使える時間」を全科目で均等振り分けると、
英語や数学などに十分な時間をまわすことができません。
このため、次のような作戦をたてました。
- 習得に時間がかかる英語や数学は受験勉強前半に集中的やる
- 習得に時間がかからない日本史は後半から本格スタートする
受験までにやること全てのことを決める
計画段階で、入試にまでやる全てのことを決めました。
具体的には次のようなことを決めました。
- 入試にまで勉強する参考書・問題集をリストアップ
- 上記の参考書・問題集を勉強する順番
- それぞれの参考書の習得に何時間かけるか
ちなみに、各参考書の習得に必要な時間は、
勉強法の本や参考書選びの本を参考にしました。
では、計画できたので実行です。
受験計画の実行と修正
予備校入学前:理解型科目の英語と数学に100%の力を注ぐ
予備校の授業は、「高校で既に学んでいること」を前提にすすめられます。
細かい段階に分かれている予備校なら、
中学レベルや高1レベル・高2レベルのこともやってくれるのかもしれませんが、
私は地方に住んでいたので「最大公約数向けの内容」しかやってくれません。
- 進学高校に3年通い、普通の成績をとった人向けの内容
- 進学高校に3年通い、「進学校の中では」成績が悪い人向けの内容
しか期待できないだろうなと考えました。
けれども、高校3年分の勉強がすっぽり抜けている私には、かなり学力差があります。
そこで、「授業で何を言っているのか全く理解できない」という状況を避けるため、
講師が授業で話している内容を最低限理解できることを目標としました。
このため、理解型科目の英語と数学に100%の力を注ぎました。
- 英語:英単語、英熟語、英文法の暗記、英文解釈
- 数学:公式の暗記、教科書レベルの問題の習得
この頃の英語勉強法は、ゼロからの英語勉強法という記事に書いています。
ちなみに、私は完全に独学で勉強しましたが、
可能なら家庭教師や個別指導塾などで、
「わからないことをすぐに質問できる体制」を作っておくと良いと思います。
その方が、ずっと早く簡単に成績があがるはずです。
でも、事情があってそれが難しい場合、気合を入れて独学しましょう。
私にできたのだから、あなたにもできるはずです。
4月⇒6月:理解型科目の英語と数学に90%の力を注ぐ
4月から予備校が始まったので、独学と並行して勉強することになりました。
この頃の勉強の方針は次の通りです。
- 予備校の勉強はきちんとする(予習と復習ベストを尽くす)
- 予備校に加え、毎日宅浪生並みの勉強をする
なぜなら、人よりもずっと低い成績からスタートして、
難関校と言われる大学への合格を目指していたからです。
人と同じペースでやっていても、絶対に間に合わないと考ました。
けれども、上記のようなやり方であれば、
「受験まで1年しかありませんが、予備校生と宅浪生の生活を同時にやれば2年分の勉強量が確保できる」と考えたからです。
ちなみに、この頃は予備校の予習復習以外では、英語と数学に全ての時間を使いました。
勉強をした内容は、予備校の授業だけでは自分には足りないと思った次のようなことです。
- 英語:英単語、英熟語、英文法の暗記、英文解釈
- 数学:公式の暗記、教科書レベルの問題の習得



夏休み:未着手の理解型科目「古文」に80%の力を注ぐ+英語の速読の練習
体験記の「初めての挫折」という記事でも書きましたが、
ここで、計画の大きな変更を行いました。
第一志望の東大の文一から早稲田の法学部への変更です。
- 数学がかけた時間の割に成績が上がらない(この時偏差値50くらい)
- 英語は偏差値60に届きそうだが、早稲田には全然足りない。もっと勉強時間が必要
- 数学に多くの時間が割かれて、古文の勉強がほとんどできていない
- このままでは国立入試・私立入試どちらも中途半端な結果になる
志望校変更により、次のように受験科目が変わりました。
変更前:英語・数学・国語・日本史・地理・生物
変更後:英語・国語・日本史
これにより、多くの科目に分散していた勉強時間を少ない科目へ集中することができます。
また、夏休み中は、夏期講習で授業を入れた時間以外はフリーになるので、
苦手なことを克服するまたとないチャンスです。
夏休みでは、気になっていた次の2点に力を入れることにしました。
- 古文を勘で読むのをやめたい(点数が不安定)
- 英語の読解スピードが遅い
この問題を解消すれば、成績がぐっと上がる予感があったのですが、
なかなか時間がとれませんでした。
ようやく自分だけの勉強時間がとれるようになったので、この2つの課題に集中してやりました。
- 古文:単語・文法の暗記、読解の練習
- 英文の「返り読み」をやめて「読み下し」をする訓練
また、夏期講習は次のような授業をとりました。
- 古典文法
- 古文読解
独学と夏期講習の勉強は、同時進行です。
独学で勉強したことを夏期講習テキストで試してみたり、
夏期講習で学んだことを、独学の時間に復習してみたりと、
この頃は、古文漬けの毎日を送っていたことを覚えています。
この時の勉強のおかげで、国語の偏差値は1ヶ月で20上昇し、古文は確実な得点源となりました。



9月⇒10月:暗記科目日本史に60%の力を注ぐ
「暗記型科目と理解型科目の違いを知っておく」という記事で書きましたが、
日本史などの暗記型科目には、
- 勉強すればすぐに点数になる
- 勉強しないと忘れてしまう
(記憶したことを忘れないようメンテナンスが必要)
一方、英語や国語等の理解型科目には
- 成績を上げるためには時間が多く必要
- 毎日勉強しないと勘が鈍る
という特徴があります。
そこで、習得に時間がかからず必要な日本史は後回しにしていました。
日本史は9月から本格スタートしました。
とは言え、それまで日本史の勉強は全くやっていないわけではありませんでした。
予備校の授業の進度に合わせて、学んだことはその場できっちり覚えるようにしていました。
例えば、授業が平安時代まで進んでいたとすると次のような感じです
- 日本史の教科書を平安時代まで読み、歴史の流れを理解する
- 日本史問題集を2冊、平安時代まで記憶する
- 模試では、平安時代までの問題は高得点をとれるように努力する
- (それ以外は、まだ勉強してないので、点数が低くてもくよくよしない)
しかし、本格スタートした9月以降は次のように勉強のやり方を変更しました。
- 予備校の授業進度とは関係なく独学で勉強を進める
- 入試に頻出する「近現代史」を中心に問題集を記憶していく
- 史料問題集を記憶する
- 一問一答で知識の漏れをチェックする
日本史の勉強にハマってくると、全ての勉強時間を日本史につかいたくなってしまいますが、英語と国語の2科目は、「毎日勉強しないと勘が鈍る」ので、毎日勉強しました。
このため、40%の力を割き、日本史には60%の力を使いました。
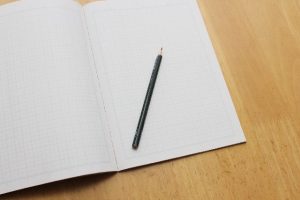
11月⇒12月:模試を受けまくる・受験テクニック習得
この頃は本番慣れするために、模試を受けまくりました。
自分通う以外の予備校の模試も受け、
特に大学別模試は全て受験したことを覚えています。
体験記の「スランプの克服」という記事でも書きましたが、
マーク模試の成績が急降下したのもこの頃です。
この原因は、連日の模試で疲れが出てきたことに加え、
部活を引退した現役生が本格的に受験勉強を開始、急激に伸びてくるからだと考えています。
彼らに追い付かれないようにするには、
私のように4月からラストスパートのように勉強するのが良いかもしれません。
さて、スランプを脱出するために必要な課題は次の2点だと考えました。
- 英語が時間不足になることがある
- 内容はわかるのに、選択肢をミスすることがある
これに対して、私が行った対策は次の通りです。
- 時間配分の練習
過去問や模試で設問毎に制限時間をきめ、時間内に問題を解き終える練習 - 英語のパラグラフリーディング習得
- 選択肢の研究
ちなみに、選択肢の研究は「本文を読まずに本番で選択肢だけを見て回答する」というテーマの本で勉強しました。
この本には、次のようなことが書かれていていました。
- 出題者が複数の選択肢をどうやって作っているのか
- 出題者が受験生をどうやって引っかけようとしているのか
- 本文中にどんな根拠を探しにいけばよいのか
これらを読んでから、英語と現代文のスピードが大幅に上がりました。
これ以降の英語の解き方は次のように変わりました。
- 選択肢だけを見て2択まで絞る
- どちらの選択肢が正しいのかパラグラフリーディングで根拠を探す
- 英文中の重要な部分、難しい部分は精読する
- 正解の選択肢を決める
なお、こうしたテクニックは、「受験テクニックについて」という記事に書きましたが、
終盤につかうと良いと思います。
実力がないまま使うと、本文中から正解の根拠を探すことがうまくできないかもしれません。
1月⇒2月:本番
入試が始まってからは次のようなことをやっていました。
- 「忘れやすいこと」「苦手なこと」をまとめたノートを記憶する
- 受験する大学の過去問の研究(設問毎の時間配分決めを行う)
- 日本史一問一答
- 英単語集・英熟語集のチェック
- 古文単語集のチェック
- 勘が鈍らないように英語と国語の問題集を解く
さらに、実際に受験をした入試で「わからないこと」や「忘れていたこと」を見つけたら、
次回からは正解できるようにその日のうちに復習するようにしていました。
受験勉強計画の立て方 まとめ
私は、以上のような計画をたてて、勉強をしました。
これは、最初からこのような計画になっていたのではなく、
実際に勉強をして、課題を発見しつつ修正した結果このようになった感じです。
そして、適切な修正ができたのは情報収集をしっかりやっていたからだと思います。
何をやればよいかわからない人は、悩んで立ち止まらず、まずは情報収集してみましょう。
そして、一人で計画を立てたり課題を見つけることが難しいという人は、
学校の先生や家庭教師・塾の先生などに相談してみましょう。
使えるものは何でも使うべきです。
最後に、計画を立てる際に一番重要なポイントは、
「習得に時間がかかる科目を前半に、時間がかからない科目を後半に重点的にやる」ということです。
以上です。






